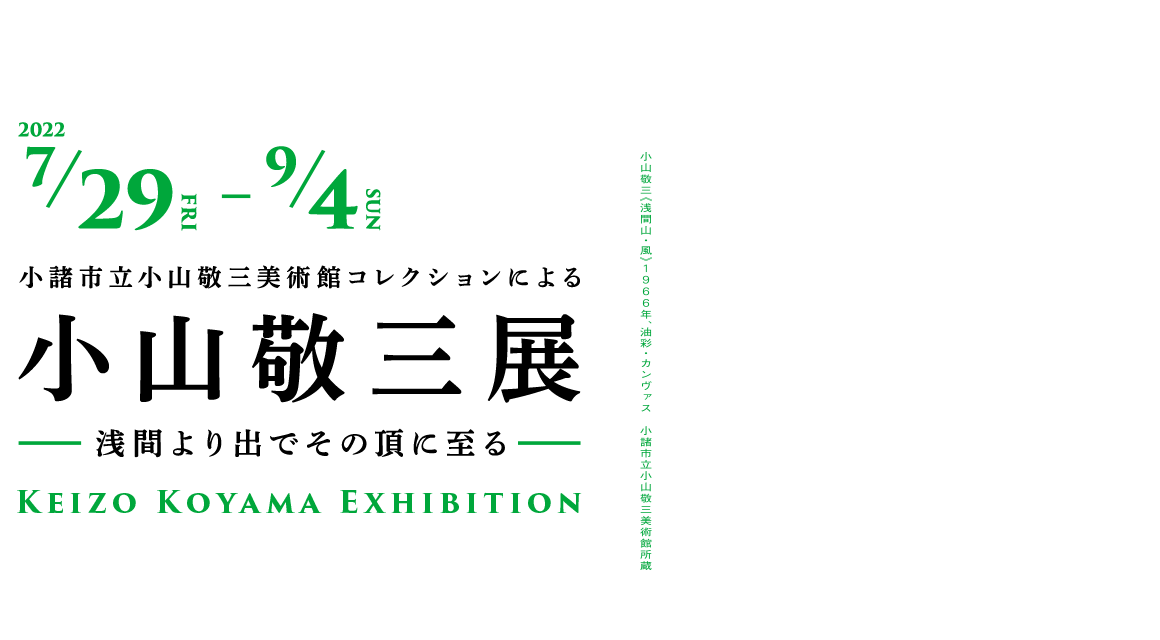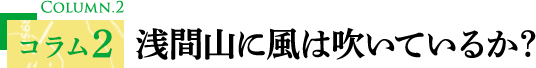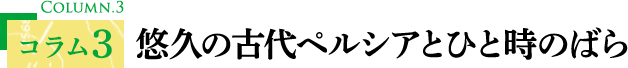はけの森美術館夏の企画展では、洋画家・小山敬三の風景画を中心とした作品を展示します。生まれ故郷の小諸、留学先のフランス、旅行で訪れた中国、そして軽井沢からの浅間山…絵だけ見ても十分に魅力的ですが、それぞれの「地理」がわかると更に楽しめるのが風景画。特設ページでは出展作品3点について、描かれたものと「場所」をめぐる情報を紹介します。

小山敬三《中仙道》1913年 水彩・紙
小諸市立小山敬三美術館蔵
《中仙道》は本展出展作の中では小山敬三の最も初期の作品で、16歳、1913年の作です。画面の手前に土がむき出しになった街道があり、向こう側には畑と林が続いていることがわかりますが、その間に大きな石灯籠と石碑が立ちはだかり、他にも宝珠の付いた石塔や小さな板碑も見えます。ここは、どこなのでしょうか。
小諸は中山道(中仙道)の宿ではないので、ここに描かれているのは小諸からそう遠くない、中山道の宿。中山道では江戸から二十番目の宿であるとともに、北国街道との分岐にあたる追分宿です。
信濃追分とも呼ばれて今でも往時の様子を感じさせる趣ある追分宿ですが、北国街道との分岐にはそれを示す「分去れの碑」が建っています。江戸からここまで共に来た人たちが、西に向かう人(中山道)は左へ、越後に向かう人(北国街道)は右へと、涙で袂を濡らしながら分かれていく別れのスポットです。
画中に描かれている石碑と石灯籠は形からまさにこの分去れの碑であろうとうかがえます。しかし、画面には涙の旅人の姿はありません。後ろで黙々と畑仕事をしている人がいるだけで、むしろひっそり静まり返る夏の昼下がりのような風情です。
小諸は中山道(中仙道)の宿ではないので、ここに描かれているのは小諸からそう遠くない、中山道の宿。中山道では江戸から二十番目の宿であるとともに、北国街道との分岐にあたる追分宿です。
信濃追分とも呼ばれて今でも往時の様子を感じさせる趣ある追分宿ですが、北国街道との分岐にはそれを示す「分去れの碑」が建っています。江戸からここまで共に来た人たちが、西に向かう人(中山道)は左へ、越後に向かう人(北国街道)は右へと、涙で袂を濡らしながら分かれていく別れのスポットです。
画中に描かれている石碑と石灯籠は形からまさにこの分去れの碑であろうとうかがえます。しかし、画面には涙の旅人の姿はありません。後ろで黙々と畑仕事をしている人がいるだけで、むしろひっそり静まり返る夏の昼下がりのような風情です。

小山敬三《浅間山・風》1966年 油彩・カンヴァス
小諸市立小山敬三美術館蔵
圧倒的な存在感を見せるのが本展メインビジュアルに採用されている《浅間山・風》。小山敬三は軽井沢の別荘からの浅間山の眺めをとても気に入っており、たびたび描いていますが、本作もそうした軽井沢の別荘からの眺めに基づいたものです。中央にそびえる浅間山が湧き立つ雲の中に堂々とした姿を見せる様子は雄大であると共に、「風」の爽快な感触を伝えています。
—ところで、この、《浅間山・風》の風はどこから吹いているのでしょう?
画面の中の雲の湧き方に注意してみて見ると、嶺の後ろから湧き上がり、一部は山肌を滑り降りるようにこちらに向かってきています。軽井沢から浅間山は北東の方向にあり、山体の南面を眺めていることになりますが、この「後ろ」側はつまり北面。蛇骨岳があり、そして、根子岳、草津白根山、苗場山、谷川連峰と連なる火山とその周りの温泉地、高原地帯が続いています。
そう言われてピンときた方もいるでしょうか。これはそのまま、長野、群馬、そして新潟の三県にまたがる上信越高原国立公園に含まれる地域にぴったり一致します。
《浅間山・風》の風はこの上信越高原国立公園を渡って、浅間の尾根にたどり着いたのです。そしてその風に含まれる水分が、尾根を滑り降りて雲になり、浅間山を眺める人の前で湧き上がったところと想像すると、壮大な自然の営みを感じさせます。
—ところで、この、《浅間山・風》の風はどこから吹いているのでしょう?
画面の中の雲の湧き方に注意してみて見ると、嶺の後ろから湧き上がり、一部は山肌を滑り降りるようにこちらに向かってきています。軽井沢から浅間山は北東の方向にあり、山体の南面を眺めていることになりますが、この「後ろ」側はつまり北面。蛇骨岳があり、そして、根子岳、草津白根山、苗場山、谷川連峰と連なる火山とその周りの温泉地、高原地帯が続いています。
そう言われてピンときた方もいるでしょうか。これはそのまま、長野、群馬、そして新潟の三県にまたがる上信越高原国立公園に含まれる地域にぴったり一致します。
《浅間山・風》の風はこの上信越高原国立公園を渡って、浅間の尾根にたどり着いたのです。そしてその風に含まれる水分が、尾根を滑り降りて雲になり、浅間山を眺める人の前で湧き上がったところと想像すると、壮大な自然の営みを感じさせます。

小山敬三《ペルシャ壺のばら》1973年 油彩・カンヴァス
小諸市立小山敬三美術館蔵
さて、最後はちょっと趣向の変わった作品を紹介したいと思います。風景画ではなく、静物画です。
卓上に置かれた小さな青い壺。カラフルなばらが活けられていますが、壺もつやつやとはっきりしたエメラルドグリーンの上に紺青の模様が入っていて、ばらに負けない存在感があります。
実はこの壺、かつて小山敬三のアトリエにあったものが今でも小諸市立小山敬三美術館に所蔵されており、実物を本展の展示室で見ることができます。名前は《ペルシャ緑霰平宝珠形鉢壺》…「緑霰平宝珠形鉢壺」というのは「グリーンの釉薬がかかっていてそこにまるで“あられ(霰)”のような点々模様がついた、やや平たいタマネギ型の容器」という意味です。
実物は絵の通り、透明感のある釉薬が全体にかけてある。とてもきれいな取っ手付きの壺。写真ではなかなかその魅力が伝わらないので展示室でぜひ実物をご覧いただければと思いますが、ところどころに土がついていて、釉薬の一部がキラキラ光る金属質の光沢を帯びています(銀化といいます)。これらの特徴はこの容器が長く土中にあったことを示しており、エメラルドグリーンの釉薬がかかっていることから古代ペルシア陶器の発掘品ではないかと想像されます。
この壺は小山敬三が骨董商から薦められて購入したもので、詳しいことはわからないそうです。ですが遠い昔、ヨーロッパとアジアの文化が出会う古代ペルシアで生まれた陶器が、長い時間を経て再び日の目を見(銀化は通常、相当程度土中にないと起こりません)、また長い旅をして日本の自身の手元に届いた…と小山は想いを馳せたのではないでしょうか。そして、小諸を旅立ちヨーロッパを目指した若かりし日の自身のことも連想したかもしれません。ばらの花の、つぼみが開き散るまでのひと時のみずみずしさと、ペルシアの乾いた砂に埋もれて悠久の時間を過ごした壺の対比は、小品ながら味わいぶかい作品です。
卓上に置かれた小さな青い壺。カラフルなばらが活けられていますが、壺もつやつやとはっきりしたエメラルドグリーンの上に紺青の模様が入っていて、ばらに負けない存在感があります。
実はこの壺、かつて小山敬三のアトリエにあったものが今でも小諸市立小山敬三美術館に所蔵されており、実物を本展の展示室で見ることができます。名前は《ペルシャ緑霰平宝珠形鉢壺》…「緑霰平宝珠形鉢壺」というのは「グリーンの釉薬がかかっていてそこにまるで“あられ(霰)”のような点々模様がついた、やや平たいタマネギ型の容器」という意味です。
実物は絵の通り、透明感のある釉薬が全体にかけてある。とてもきれいな取っ手付きの壺。写真ではなかなかその魅力が伝わらないので展示室でぜひ実物をご覧いただければと思いますが、ところどころに土がついていて、釉薬の一部がキラキラ光る金属質の光沢を帯びています(銀化といいます)。これらの特徴はこの容器が長く土中にあったことを示しており、エメラルドグリーンの釉薬がかかっていることから古代ペルシア陶器の発掘品ではないかと想像されます。
この壺は小山敬三が骨董商から薦められて購入したもので、詳しいことはわからないそうです。ですが遠い昔、ヨーロッパとアジアの文化が出会う古代ペルシアで生まれた陶器が、長い時間を経て再び日の目を見(銀化は通常、相当程度土中にないと起こりません)、また長い旅をして日本の自身の手元に届いた…と小山は想いを馳せたのではないでしょうか。そして、小諸を旅立ちヨーロッパを目指した若かりし日の自身のことも連想したかもしれません。ばらの花の、つぼみが開き散るまでのひと時のみずみずしさと、ペルシアの乾いた砂に埋もれて悠久の時間を過ごした壺の対比は、小品ながら味わいぶかい作品です。